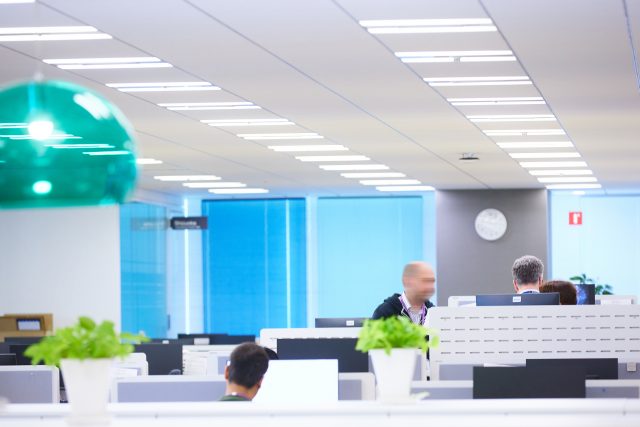Popular Tags
この企業をもっと知る

KDDI株式会社
通信業界大手のKDDIが、設立以来初と言える大がかりな人事改革に着手。その本丸である「KDDI版ジョブ型人事制度」導入についての背景や具体的な取り組みについて話を聞いた。
Official Site携帯電話3大キャリアの一つである「au」をはじめ、さまざまな通信事業を展開するKDDI株式会社が、設立以来初と言える大がかりな人事改革に着手した。2020年8月には「KDDI版ジョブ型人事制度」を導入し、社員の生産性向上などを推し進めている。改革の背景や具体的な取り組み内容について、同社コーポレート統括本部 人事本部 人事企画部 部長の長野修平さんと、人財開発部 新卒採用グループの小林真理奈さんに話を聞いた。
目次

若手のチャレンジ意欲を高めたい
会社設立から20年余りが経った今、さらなる高みを目指すKDDIにとって、事業領域の拡大が喫緊の課題となっている。
——事業内容について教えてください。
長野さん 通信事業を柱として、国内および海外での携帯電話サービスに加えて、固定電話やインターネットサービスなどを提供しています。ただし、国内の通信市場は、今後飽和状態となっていくと予想されるため、新規事業へのチャレンジとして、昨今は金融やエネルギーといった市場にも参入しています。
——2020年8月に「KDDI版ジョブ型人事制度」を導入しました。その背景は?
長野さん まさに、多岐にわたる新たな事業に挑戦する上で、人事制度改革は不可欠でした。これまで通信事業を中心に人材を育成してきたため、どうしてもスキルなどに偏りがありました。これからは新しい事業でも活躍できる人材を、外部から採用したり、内部で育ててキャリアシフトさせたりしなければなりません。人事制度もそれに適した形にする必要があり、ジョブ型の新制度を導入する運びとなりました。
また、将来のKDDIを支える若い社員たちのチャレンジ意欲が薄いという課題もありました。従業員エンゲージメントに関する調査をしたところ、「挑戦」の項目において若手はスコアがそれほど高くはありませんでした。KDDIは発足当初からチャレンジ精神をDNAにしてきましたが、20年ほど経つ中で、社員構成や職場の風土も変わり、それが一因になっているのだろうと認識しています。そこで、若者を含め、全ての社員にあらためて魅力に感じてもらえるような人事制度にし、KDDIにいることで多くのことに挑戦でき、自分の成長につながるという点を強く打ち出していきたいと考えました。
——新制度とはどのようなものでしょうか?
長野さん 働いた時間ではなく、成果や挑戦、能力を評価し、処遇に反映し、人財を育成することを目的にしています。特徴としては、大きく2点あります。
一つは、狭い範囲の専門性を極めるのではなく、もう少し大きなくくりで専門性を高めていけるようにしたことです。あまり狭くすると、人材の固着化を招き、総合力がつかなくなるためです。ジョブの定義をできるだけ大くくりにして、幅広い人材を育成できるようにしました。
もう一つは、KDDIフィロソフィという企業理念で掲げている「人間力」を評価する点です。そういった社員のコアスキルに着目し、専門性以外の部分も引き続き評価していくメッセージを打ち出しています。

——大きなくくりとは、具体的に?
長野さん 30から成る専門領域です。当社の事業規模を考えると少ないでしょうが、全社員が何かしらの領域に属せるように設定しました。例えば、人事だと、採用や給与など細かくジョブを分けることはできますが、「人事」という一つのくくりで定義しています。
あとは、新たにDX(デジタルトランスフォーメーション)関連のジョブも設定し、社員の挑戦を促しています。こちらは、「データサイエンティスト」「エクスペリエンスアーキテクト」「ビジネスディベロップメント」「コンサルタント&プロダクトマネージャー」「テクノロジスト」といった領域があります。
——30領域に絞り込む上で、工夫した点は?
長野さん 専門領域というと、どうしても技術寄りの定義になりがちです。実際、運用部門やバックヤード部門、営業部門の仕事の専門性とは何か、といった意見はありました。そこで人事部以外にも、各事業の責任者をプロジェクトにアサインするとともに、世間一般的なジョブの定義を示しながら、専門性に関する議論を進めていきました。

——社員一人ひとりの領域はどのように決まっていくのでしょうか?
長野さん 月に2回行われる上司との1on1ミーティングの中で、「自分はこの専門性を磨いていくんだ」という本人の意思と、上司のアドバイスを基に決めていきます。
小林さん また、中途入社の場合はポジションごとに採用するため、応募段階で専門領域が決まります。新卒採用については、「OPENコース」と「WILLコース」があり、WILLの場合は初期配属の領域を確約しています。例えば、ネットワークのインフラエンジニアを希望すれば、初期配属では必ずその領域の仕事に就けます。それぞれのジョブを説明しながら、ミスマッチが起きないように採用活動を行なっています。
——他方、管理職社員のジョブの定義はどのように行なっていますか?
長野さん これまでの管理職の概念を変えて、「経営基幹職」としました。従来の管理職やリーダーというと、マネジメント業務が中心でしたが、それだけにとどまらず、専門性の面でもしっかりとメンバーを指導でき、社外でも通用する能力を兼ね備えるべきだと再定義しました。
会社設立以来の人事改革
——新制度に対する社員の反応はいかがでしょうか?
長野さん 若手については、好意的に受け止めてもらっている印象です。実力に応じて処遇されることや、専門性を磨けるというニーズはあると把握した上での施策だったので、そこは響いたのかなと思います。
一方で、比較的社歴の長い社員については、会社発足以降、初めての大規模な制度改革であるため、ある意味でショックを与えた面もあるようです。実際に、不安視する声やネガティブな意見もありましたが、説明会や対話を通して、改革の意義、目的を理解いただきました。
新制度は2020年8月に導入しましたが、まずは中途入社した社員から始めて、既存の社員に対しては段階的に適用していきました。その間に説明会や経営層とのタウンホールミーティングなどを実施し、新制度に対する理解を深めてもらう機会を作りました。全社員に適用されたのは今年4月ですので、具体的な反応が出てくるのはこれからです。

——KDDI設立以来の大規模な人事制度改革ということですが、どのくらいのインパクトだったのでしょうか?
長野さん 当社の人事制度には、等級制度、評価制度、報酬制度に加えて、採用、育成、人員配置といった人材マネジメントに関するものもあります。今まではそれぞれをバラバラに、かつ小さく改善していました。今回は、KDDI版のジョブスクリプション(職務記述書)をしっかりと固めた上で、同じタイミング、同じコンセプトで人事制度すべてに手を入れました。ここまでの取り組みは初めてです。
全社員の人事情報をオープンに
——導入後、どのような変化があったでしょうか?
長野さん 全社員が今後のキャリアを考える機会が生まれました。これまでもキャリアプランは書いていましたが、新制度をきっかけに、専門性をどう高めていくのか、どういうジョブに進んでいくかを具体的にアプトプットするようになりました。
また、各自のキャリアプランをタレントマネジメントシステム上で全社公開しています。最初は任意でやってもらっていましたが、なかなか進まないので、昨年から基本的には約1万3000人いるKDDI本体の全社員必須という形に変えました。
新規事業開発を担う部署が働くフロア。他部署でもここで働くことも出来る
——キャリアプランをオープン化したことによる効果は何ですか?
長野さん 人材情報はこれまで所属長と人事担当者だけが見るものでした。従って、人事異動は、所属長が自分の人脈を駆使して最適な社員を見つけてくるといった要素が大きく、非常にクローズドなものでした。人材情報をオープンにしたことで、システム上から適切な社員を探せますし、社員側からも「この部署に行きたい」とアプローチできるようになりました。今後はどんどん自律的に人事異動が行われていくことを目指しています。
既に積極的な社員は、社内の公募制度や副業制度を活用して、新たなキャリアを築こうとしています。副業制度とは、就業時間の約20パーセントを自部署以外の業務に充てられるというもので、仮にその仕事が自分に合っていれば、公募などがあったタイミングで異動することも可能です。
——副業制度に関して、具体的な事例はありますか?
長野さん 例えば、コーポレート部門のスタッフが地方創生に携わりたいということで、地方の案件にチャレンジしたケースや、お客さま目線でauの今後の事業を検討する50人規模のプロジェクトに参画した社員もいます。
小林さん 実は、私も社内副業の経験があります。元々は法人営業を担当していて、以前から新規事業の企画に携わりたいと思っていました。そこで半年間、新規事業プロジェクトのメンバーとして活動しました。新規事業に対して興味を持つ学生も多いため、自分の言葉でその面白さなどを話せるのは、採用担当としても必要だなと実感しています。
データドリブンで人事を強くする
KDDI版ジョブ型人事制度の導入に合わせて、働き方に関する新しい指針を発表。それが「KDDI 新働き方宣言」だ。
——「KDDI 新働き方宣言」について教えてください。
長野さん 時間や場所にとらわれないで、成果を出す働き方を目指すことをコンセプトとしています。当社の働き方として、オフィスワーク中心の「Sitter」、社内外での打ち合わせが多い「Walker」、営業のように外勤中心の「Runner」、そして組織のリーダーである「Manager」という4つのモデルケースに分類しました。
社員のワークスタイルに合わせて、執務室以外にも様々な働く場所が用意されている
それぞれのワークスタイルに応じて、社員一人ひとりがパフォーマンスを高めることができるよう、具体的には、大きく4つの取り組みを進めています。
1つ目は、オフィス拠点を集約したり、ウェブ会議の環境を整えたりと、働く場所のあるべき姿について検討しています。2つ目が、社内DXです。セキュアPCを導入して、どこでもモバイルワークできる環境を用意しています。
3つ目は、社員の働き方に関するデータを可視化する取り組みです。どういう業務に、どれだけの時間を費やしているかを見える化することで、生産性や業務効率を高める働き方の提案を行なっていきます。最後は、社内に新しい働き方を浸透させていくワーキングです。好事例を社内で共有したり、生産性に関するサーベイをしたりして、社員の意識を高めています。
高層階のラウンジは開放的でグリーンを散りばめた空間になっている。休憩や雑談だけでなく、ここで働くことも出来る。
——先ほどの4つのモデルケースについて、何か成功事例はありますか?
長野さん 例えば、Runnerの社員は、オンライン営業やリモートワークなど、これまでのワークスタイルと違う働き方にチャレンジしています。営業だと、資料作成の時間を確保しながら、顧客訪問もしなくてはなりません。オンラインで営業活動ができるようモバイル環境を整備したことで、営業成果につながったという声を聞いています。制度面でも今年4月からコアタイムがなく、好きなタイミングで仕事ができるようなフレックス制度に変えました。
今では自分たちの働き方自体を商材として、顧客に提供する流れもできつつあります。実際、コロナ禍で引き合いは増えていて、われわれ人事部門も営業から依頼を受けて、社内の制度の紹介などを客先で行なっています。
最近多いのは、働き方のデータ活用についてでしょうか。従業員のエンゲージメントやワークスタイルなどのデータを取得、分析して、いろいろな施策に生かすという「データドリブン人事(HR)」をしばしば紹介しています。

——データドリブンHRとは具体的に?
長野さん 勤務時間、テレワーク時間、メール時間、会議に使っている時間、どういう社員とコラボして仕事をしているかなどのデータを、PCのログや勤務管理システムから集めて、参照しています。あとは、エンゲージメントサーベイの結果などを重ね合わせて、ロールモデルとなる働き方と現状との比較などを見えるようにしています。これらの材料をどうやって使っていくのかは、まだまだこれからですが、アイデアはあります。
例えば、先ほどお伝えしたように、当社は1on1ミーティングを重視しています。その場で上司とメンバーが話すテーマは多岐に渡りますが、データに基づいた対話もできるようにしたいです。その日のテーマを一つ決めるにしても、システム側から「今日はこのことを話したらいい」というリコメンドができたらいいですね。すぐに働き方に関するデータを参照できて、お互いの対話の質も上がるようなサポートができたら嬉しいです。

自らを変革できる人材が活躍できる
——今後に向けた課題はありますか?
長野さん 人事制度については、あくまでコンセプトを固めて、導入した段階です。これを社員に使い倒してもらわないと意味がありません。そのために必要な要素がデータドリブンHRだと考えています。データを活用してもらえる環境を社員に提供していきますが、これは人事部門だけでやっていても進まないはずです。各部門の担当者とのグリップを強化していくことも重要だと感じています。

——これから先、KDDIが求める人材像とはどのようなものでしょうか?
長野さん 自らキャリアを考え、プロフェッショナルとして成長し、イノベーションや挑戦をし続ける人財です。持続的に成長しながら、サステナブルな社会に貢献していく会社として、人の力は不可欠です。ぜひプロフェッショナルな人に来てもらいたいですし、KDDIで働くことでプロに育ってもらいたいです。
小林さん グループ会社を含めると100社以上もあるため、そのアセットをうまく使って、自分のやりたいことを実現したり、社会に貢献したりできます。能動的に自らを変革したいと思う人にとっては活躍できるフィールドが用意されています。ぜひチャレンジしてほしいですね。
この企業のことをもっと知る
取材のウラ側
誰もが知る大企業であり、日本の社会インフラを支えている事業を展開していることから、正直なところ、ビジネス的には安泰といっても過言ではないだろう。けれども、そうした現状に満足せず、いや、むしろ危機感を持って、新境地を開こうとする姿勢に好感を持った。
実際、取材の中で「挑戦」や「チャレンジ」という言葉が繰り返し使われたことは、その証左であろう。また、それは単なる掛け声ではないことも示された。例えば、約1万3000人の社員の人事情報をオープンにするといった取り組みは、本気で会社を変革するためのチャレンジ以外の何者でもないはずだ。
この企業との繋がりを希望する
採用情報を見る
気になる

 137
137